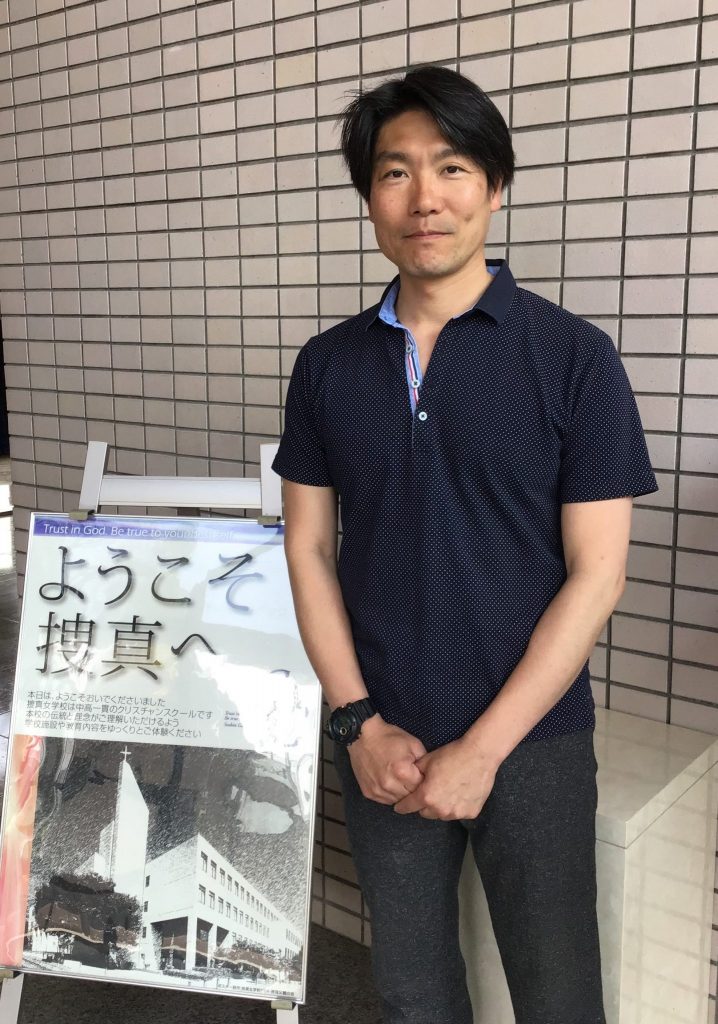私は1982年4月、捜真女学校に社会科教諭として採用して頂きました。日野綾子先生が校長、千葉勇先生が理事長の時代です。その後、宗教科教員免許状を取得し2005年3月まで主に聖書・世界史・倫理を教えていました。宗教科教員免許状の取得に際しては日野綾子先生に本当にお世話になりました。
22年間の捜真在職中の思い出は、生徒達(卒業生)、先生方、礼拝、授業、行事等々…数えきれません。中でも特に思い出深い事の1つに自然教室があります。聖書を教えていましたので、毎年、中学部・高等学部の各々1学年の自然教室の主題講演を担当させて頂きました。60分(高校生は90分のこともありました)の講演が2~3回ありました。校外の宿泊行事ですから長い講演は眠気が襲ってきます。それでも一生懸命に聴こうとする生徒達の顔が浮かびます。特に高3の自然教室は“最後”という事もあり特別だったように思います。
主題講演も琴線に触れるような内容の時には、集中した真剣な眼差しを注いでくれました(高3の真剣な眼差し…これは普段の礼拝でも同様だったように思います)。
ある年度の高3の自然教室は
主題「交わり」、主題聖句“あなたの隣人を愛せよ”(マルコによる福音書12章24節~)でした。主題講演(90分)が4回、講演後には自由参加のディスカッション(30分)があるという非常にヘビーなプログラムでした。講演の要点は以下のようなものです。
・神様の交わりの対象=愛の対象として人間は創られている。
・人間同士も互いに交わりを持つように=互いに愛するように=相手の人格を尊重するように創られている。
・しかし人間の現実は他者をまるで“モノ”のように“手段”として扱う状況に満ちている。
・その原因は神様を認めず自己を絶対化している事にある。
・神様を認めず自己を絶対化した結末は人類の悲惨な負の歴史が物語っている。
そして、具体的な人類の悲惨な出来事として“ナチスドイツによるユダヤ人虐殺”と“カンボジアのポル・ポトによる虐殺”の話をしました。この年の3月にカンボジアを訪れた事もあり“ポル・ポトによる自国民大虐殺とその後のカンボジアの現状”についてはかなり詳しく話ました。
講演の回が進む度にディスカッションに参加する生徒の数も増え続け、最後には全員参加!?と思うほどでした。
自然教室の後、高3の生徒達は各クラスで「カンボジアの子供達のために何かしよう。」と話し合い、学年として「全校生徒に呼びかけノート、鉛筆などを集めて贈る」ということになりました。受験期であるにもかかわらず、協力を惜しまずに時間と知恵を出し合って、文具を集め整えてカンボジアの子供達に贈りました。これがカンボジアに学校を建てる活動やカンボジア研修の最初の一歩となりました。この時の高3の生徒達はまさに“あなたの隣人を愛せよ”を実践したと言えると思います。生徒達は誰も内に秘めている力・可能性を持っていると思い知らされました。と同時に捜真の支柱は毎日の礼拝・自然教室をはじめとするキリスト教教育であると再確認しました。
昨年20年振りに捜真で中・高1度ずつ礼拝のお話をさせて頂きました。久しぶりに捜真を訪れた際、日野綾子先生が仰っていた“捜真ファミリー”という言葉を思い出しました。あっという間に時が戻ってしまい、まるで“実家”にでも帰ったようで、捜真に育てて頂き多くの方々にお世話になった事を想いました。そして何よりも、創立以来ずっと守られてきた礼拝が変わらずにとても大切にされていることは感慨深いものでした。中・高共に、静かにチャペルに入場し、綺麗に讃美歌を歌い、静かにお話を聴き、静かに退場する、整えられた礼拝が20年前と変わらず厳粛に守られていました。
神様のご計画によって建てられ130年以上の長きにわたって神様が導いて下さった捜真の伝統は毎日の礼拝を大切にすることによって守り伝えられてれていると感じました。これからも神様の豊かな祝福のもとに、み心にかなった歩みが続きますようにと祈っております。
2025.2.7 公開